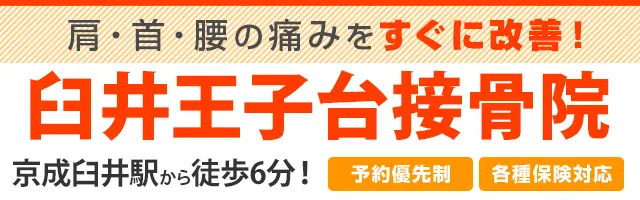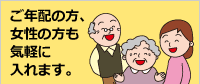オスグッド


こんなお悩みはありませんか?

小中学生でバスケットボールやバレーボールを行っており、スポーツ中に痛みを感じる
膝を曲げ伸ばしする際に疼痛がある
日常生活の中でも、ふとした動作で膝に強い痛みを感じる
ジャンプ力の低下が見られるようになった
突発的なダッシュで痛みを感じ、タイムの低下が見られるようになった
膝前面の痛みが軽減されない
オスグットについてで知っておくべきこと

まず、オスグッドとは、成長期に起こりやすいといわれている膝のスポーツ障害の一種です。特に成長期に運動をされる方に多く、男女を問わず発症する可能性があるとされています。
成長期には骨の成長と筋肉のバランスが取りづらくなるため、膝に負荷がかかり、痛みを伴うことが多いといわれています。特にジャンプの着地時やスクワット動作、膝を深く曲げた際に痛みが出やすいとされています。
ただし、学生に多く見られる症状であることから、痛みを放置してしまい、医療機関を受診しないケースも少なくありません。そのため、早期の施術をおすすめしております。
症状の現れ方は?

個人差はありますが、オスグッドの症状の現れ方についてお伝えいたします。
初期段階では、運動時や運動後に膝に痛みを感じることが一般的です。この時期にオスグッドに気づく方は少なく、痛みや症状を放置してしまうことが多いです。その後、脛骨粗面という膝の一部が突出し、膝を曲げ伸ばしすることが困難になるケースがあります。
痛みは徐々に増していき、安静時にも痛みを感じることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。また、オスグッドを放置したまま大人になった場合でも、運動時や運動後に痛みが出ることがあり、後遺症が残ることがあります。
その他の原因は?

オスグッドの原因として、膝のお皿(半月板)の下にある脛骨(すねの骨)の一部が太ももの筋肉に引っ張られることにより発症します。膝を曲げたり伸ばしたりする大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)は、膝をまたいで脛骨に付着していますが、激しく膝を曲げ伸ばしすることにより、筋肉が骨を引っ張ります。
成長期の小・中学生の骨はまだ弱く柔らかいため、筋肉が繰り返し脛骨を引っ張り、その結果、軟骨などが剥がれて炎症となり、痛みが生じることがあります。
また、太ももの筋肉が太く発達しているお子さんは、オスグッドを発症しやすいとされています。キックやシュートを行うサッカーや、ジャンプを多く行うバスケットボールをされているお子さんも、オスグッドになりやすいと考えられています。
オスグットを放置するとどうなる?

発症したオスグッドは、初期の段階で運動を控えたり、適切な処置を行うことで重症化を防ぐことができます。しかし、適切な処置を行わずにそのまま運動を続けたり、安静にし続けることによって発生する問題もあります。
オスグッドを放置して運動を続けた場合、最悪の場合、骨が剥がれ、剥離骨折となり、手術が必要になる可能性もあります。また、オスグッドを放置して運動を中止し、安静にし続けることにより、身体の成長を促す成長ホルモンの分泌が減少し、骨や筋肉の成長が妨げられる可能性もあります。
運動を続けても、安静にし続けても良い結果は得られません。そのため、原因をしっかりと把握し、適切な対応を行うことが大切です。
当院の施術方法について

オスグッドは膝の骨に痛みが生じるため、骨に対して施術を行ったり、安静にしたりと考える方も多いかもしれません。しかし、オスグッドにおいて最も重要なのは、大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)の使い過ぎによる筋緊張です。
当院では、大腿四頭筋を緩め、常に負荷がかかりにくくなるような施術を行います。まず最初に行うのは、筋肉を緩める「手技」と「筋膜ストレッチ」です。大腿四頭筋自体はもちろん、その周囲の股関節周りや太ももの裏側の筋肉も緩めていきます。
さらに、全身の骨盤矯正を行います。骨盤や体のバランスが崩れると、大腿四頭筋への負荷が増加します。そのため、足首から首までの全身のバランスを整えることで、大腿四頭筋への負荷を軽減し、結果的にオスグッドの症状の軽減が期待できます。
改善していく上でのポイント

オスグッドの症状の軽減において重要なポイントは、痛みや異変を感じた際にいかに早く対処するかです。小・中学生のお子さんが膝の下に痛みや違和感を感じた場合、オスグッドを疑い、できるだけ早く病院や接骨院に相談することをお勧めします。
また、痛みがあるからといって安静にし続けることは、成長を妨げる可能性があると考えられています。そのため、ももの筋肉を緩めながら、適度な運動を行うことが大切です。
さらに、痛みが一時的に無くなったからといって通院をやめてしまう方がよくいらっしゃいますが、痛みが無くなったことがすなわち「治った」わけではありません。痛みが無くなった後も一定期間、施術を継続することが重要です。